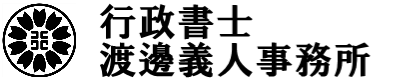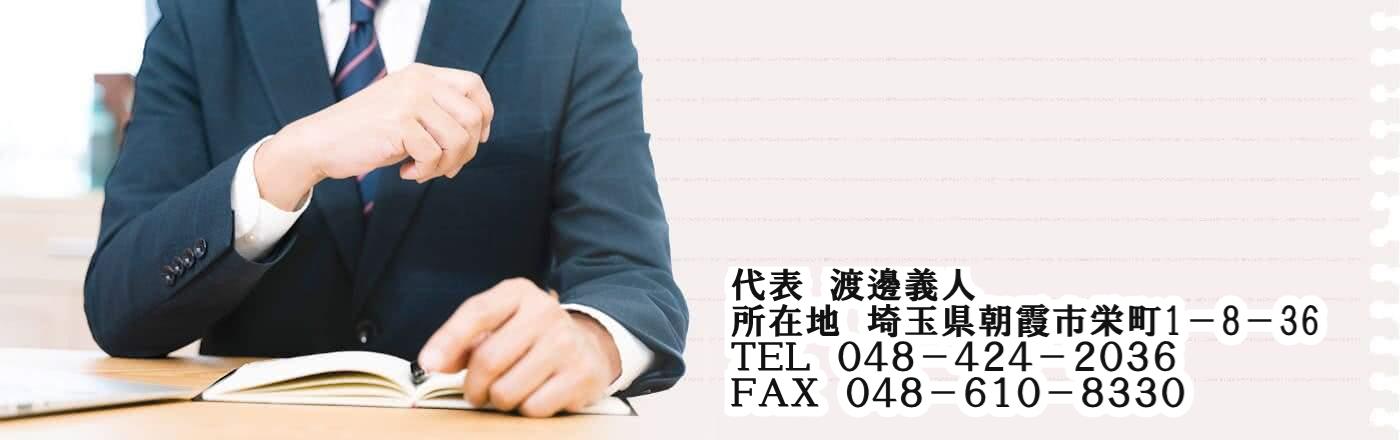法的に有効な遺言書の書き方は?②

⑷付言で思いを伝えるようにしてください。付言は通常、財産の配分が書いてある本文に続いて最後に書き添えます。
具体的には例えば「ありがとう!」「大好き!」「がんばれ!」などのライトなメッセージや財産を分ける理由、昔の思い出やエピソード、今後へのエール・激励、財産のストーリー、感謝のメッセージ、使い道の希望など、いわゆる遺言者さんの想いです。
付言には法的効力はありませんが、これが書いてあるのと無いのとでは遺言書を読んだ人の印象が全く違います。特に、偏った内容の遺言書には「想い(ハート)」が絶対必要です。
よく「財産の配分を偏った内容にしちゃったからモメたんだ」と言う人がいますが、必ずしもそれだけが原因でモメているわけではありません。「配分は偏っているけど愛情には差がないんだ」ということを伝えていないからモメるのです。ですので一言でも良いので付言を書くことをお勧めします。
⑸日付と氏名は正確に記載し、押印は実印を使うようにしてください。書いた日付の年は西暦でも和暦でも大丈夫です。氏名はもちろんフルネームで書きましょう。自筆証書遺言に押す印鑑は拇印、認印、銀行印、三文判、実印(印鑑登録印)のどれでも有効ですが、お勧めするのは実印です。遺言書の内容に不満を持つ相続人は、本当に遺言者が押した印鑑なのか疑問に持ち重箱の隅をつついてくることがあります。そんな時でも印鑑証明書を同封した実印を見せれば説得力が違います。なお印鑑登録証明書は死亡届を出したら取れなくなるので事前に用意することが必要です。
ちなみに拇印やシャチハタ印はあまりお勧めできません。前者は本人のものと証明する鑑定(鑑定費用数10万円)が必要になります。後者はインクですから印影が鮮やかすぎて印刷と間違えられやすいからです。印鑑の押し忘れは論外でトラブルの元になりますので、絶対に忘れないようにしましょう。
またもし遺言書が2枚以上になってしまう場合は、遺言書の一体性を明らかにする観点から、ホッチキスで綴じて両ページにまたがるように押印(本文に押した同じ印鑑)してください。これを「契印(けいいん)」といいます。契印がなされていない遺言書でも法的に問題ありませんが、1枚だけ紛失してしまったり、何者かに抜き取られたり差し替えられるリスクがありますので、契印しておいたほうが無難です。
⑹誤記訂正のない遺言書に仕上げるようにしてください。前記でも取り上げましたが、誤記訂正の方法は民法に定められており、せっかく誤記に気付いても訂正の仕方を間違えると遺言書が無効になりかねません。ですのでそもそも誤記訂正する事態とならないよう、面倒でもまずは鉛筆で下書きをしておき、その上からボールペン等で書くことをお勧めします。いきなり本番を迎えるよりもリハーサルをしておいたほうが間違えは起こりにくいものです。ただし、書き上げたら消しゴムで鉛筆の跡を消すのを忘れないようにしましょう。
自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければ無効ですが、民法改正により、財産目録に限って別紙として添付する場合は自筆で書かなくてもよくなりました。ただ、自筆でない財産目録を添付する場合は、いずれの財産目録も全ページに必ず遺言者が自分の氏名を書き、押印をしてください。そして本文と一緒にホッチキスをして契印を押しておいたほうが無難です。
以上が自筆証書遺言を書く際の注意点になります。自筆証書遺言にもメリット・デメリットがあります。ご自身の現状を踏まえた上でより負担の少ない適切な方法で遺言書を作成されることをお勧めします。