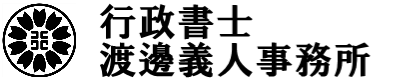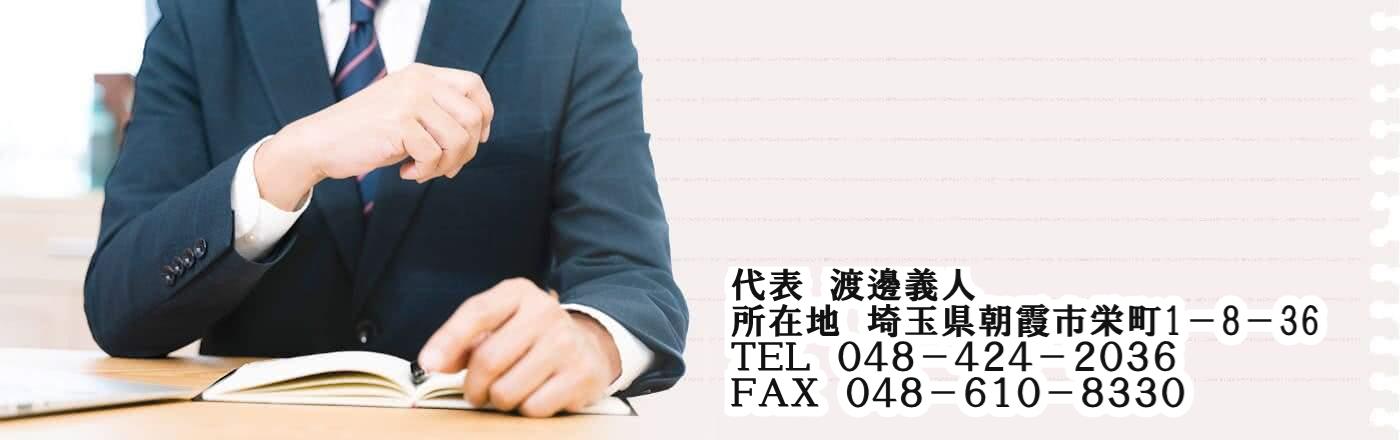遺言書は書き直せるが、認知症の人には勧められない

遺言書は書いた後でも、本人であれば新しく書き直すことができます。この場合、日付の新しいほうが有効になりますが、念のため書き直したら古い遺言書はシュレッダー等で破棄しておきましょう。古い日付の遺言書だけが先に見つかり、遺言執行も終えた後で新しい遺言書が見つかるということもあり得ます。そうなると遺言執行がやり直しになってしまいます。
撤回する方法ですが、自筆で書いた遺言書を手元で保管している場合は、シュレッダーで裁断するのが一番手っ取り早いです。法務局に遺言書を保管している場合は「保管申請の撤回」をして遺言書の返還を受けてから裁断します。
一方、公正証書遺言の場合はシュレッダーに入れても撤回することにはなりません。
なぜなら原本が公証役場に保管されているからです。そのため「私はこの遺言書より前に作った遺言書は全て取り消し、撤回する。」という遺言書を書くことではじめて撤回ができます。
書き直せるということは言い換えればやり直せるということでもあります。一方、相続対策で遺言書とよく比較される生前贈与は原則やり直すことができません。
例えば「近々、同居して老後の世話をしてくれるようなことを言っていた息子に自宅を贈与しよう」と贈与契約書を交わし、移転登記も終えていたAさんがいたとします。しかし、いざふたを開けてみると嫁姑の些細なケンカがきっかけで息子夫婦は同居どころか自宅に寄り付かなくなり、孫も遊びに来なくなってしまいました。
このような場合でも、一度履行した贈与は撤回できません。仮に「当てが外れたから家の名義を返してくれ!」とAさんが言ったところで果たして息子が応じるでしょうか?高い贈与税もかかりますし、まず無理でしょう。生前贈与はやり直しが効かないのです。
これがもし遺言書だったらどうでしょうか?上記のような理由で、息子に自宅を遺す内容の遺言書を書いてあったとしても、もし息子の態度が期待していたものと違うので自宅を息子に遺すのを無かったことにしたい、となってもその実現は簡単です。遺言書を撤回するか書き直せばよいのです。
遺言書は書くときも撤回するときも、息子はもちろん誰にも同意を得る義務はありません。一方、生前贈与は自分だけで勝手に無かったことにはできません。贈与したものはもう相手のものだからです。
なお、1つだけ注意があります。遺言書を勧める場合、本人が認知症になっている場合は避けたほうが無難です。判断能力(=意思能力)のない人が書いた遺言書は法的に無効になるからです。
本人の判断能力の有無をめぐって、後に相続人同士で揉めては大変です。認知症の程度はさまざまなので判断能力のある軽い認知症の人であれば有効に書くことはできるかもしれません。しかし、実際には判断能力があって書かれた遺言書であるかは、疑義の出やすいところになります。そうならないためにもやはり元気なうちに書いておきましょう。