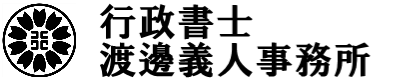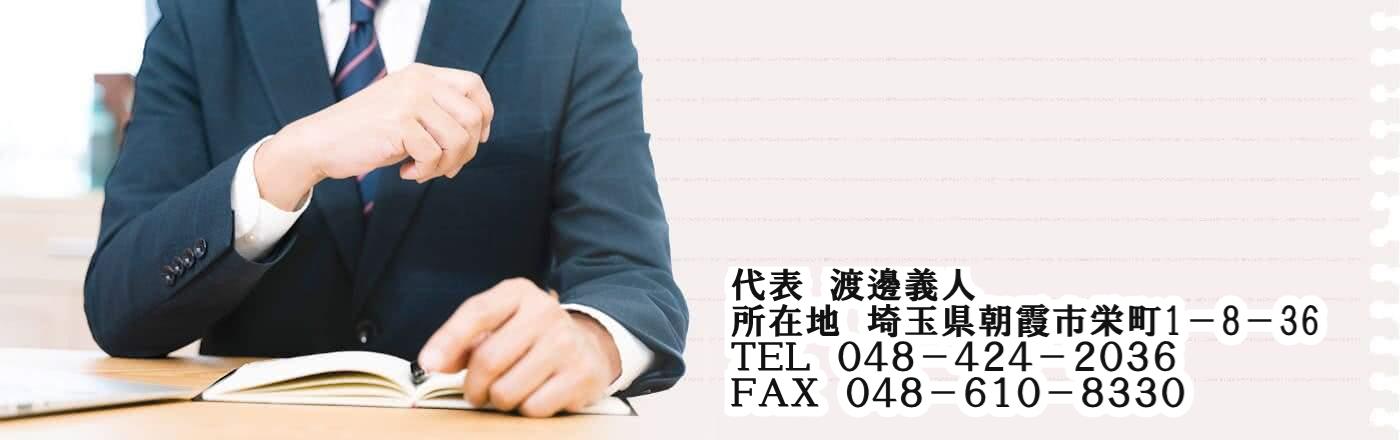法的に有効な遺言書の書き方は?①

遺言書を自分で書く「自筆証書遺言」は誰もが費用をかけずに手軽に遺言書を作れる方法です。ですが書き方に不鮮明な点や不正確な点があると、トラブルの元になったり遺言書自体が無効になったりしてしまい、せっかく努力が水の泡になってしまいます。では法的に有効でトラブルを避けられる遺言書を書くためにはどんなことを気をつければ良いのでしょうか?
⑴文章のタイトルは「遺言書」としてください。中には「遺書」でも良いのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、「遺言書」と「遺書」は字面が似ているだけで全く別物です。遺言書は法的な効力があり自分の愛情をまわりに分け与える積極的なメッセージであるのに対し、遺書は法的効力はなく自死を選ぶ人が死の直前に書き記したメモ書きで消極的なメッセージになります。ですのでタイトルは「遺言書」1択です。
⑵遺す相手を特定する情報を記載する際、文末は「相続させる」か「遺贈する」かを明記してください。文末についてはどの立場の人に遺すかによって書き方が異なります。相続人に遺す場合は文字通り「相続させる」と書いてください。一方相続人以外の人(嫁、孫、甥、姪、従妹、他人)や法人に遺すときは「遺贈する」と書いてください。くれぐれも「任せる」「贈与する」「渡す」等の表現はややこしく、見る人によってはいかようにも取れてしまいますので避けましょう。
また遺す相手が相続人であれば続柄、氏名、生年月日を書きましょう。相続人以外であれば氏名、生年月日、住所を書きます。特に相続人以外(友人等)の場合は遺言者から見た続柄がないので、特定するためには住所が必須です。氏名や生年月日だけでは同姓同名がいるかもしれません。住民票を取ってもらいそれを見ながら正確に書きましょう。
遺す財産を特定する際は、不動産は「不動産登記事項証明書」どおりに書き、預貯金は金融機関名、支店名、種類、口座番号を書いてください。株式がある場合は預託先金融機関、支店名、口座番号、銘柄、株数等を書き、自動車がある場合は車検証に記載どおりの内容を書きましょう。
特に口座番号は一桁も間違えないように書いてください。もし間違いに気づいたらきちんと訂正をしてください。ただ、訂正の仕方も民法で決められています。それを守らないと遺言書が無効になりかねないので、もう一度最初から書き直した方が無難です。
遺言書に書いていない財産があり得る可能性がある場合は遺言書に
「私は本遺言書に記載していないすべての財産については○○へ相続させる(遺贈する)」と書いておくことをお勧めします。そうすれば遺言書に書いていない財産について改めていちいち相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印(実印)をして全員の印鑑証明書を集めるという面倒を避けることができます。
⑶遺言執行者を定めるようにしてください。遺言執行者は遺言書の内容を具体的に実現させる人の事です。いくら遺言書が書かれてあるといっても、遺言者本人が亡くなると自動的に不動産の名義が変わったり、預貯金が払い戻されるわけではありませんので、遺言書の内容を実現する行為が必要となります。
遺言執行者は必ず指定しないといけないわけではありませんが、指定されている場合とされていない場合とでは、手続き先の必要書類が異なってきます。また遺言執行者の記載がなければ相続人との協議で決めるケースが多いですが、そこでモメる場合もありますので、やはり遺言書に記載しておいたほうが無難です。
相続人を遺言執行者に指定する場合は、特に金融機関に複数回足を運ばないといけないのでやはり平日の日中に動ける人がお勧めです。なお、遺言書の内容に不満を持つであろう相続人を遺言執行者に指定することは避けるようにしましょう。